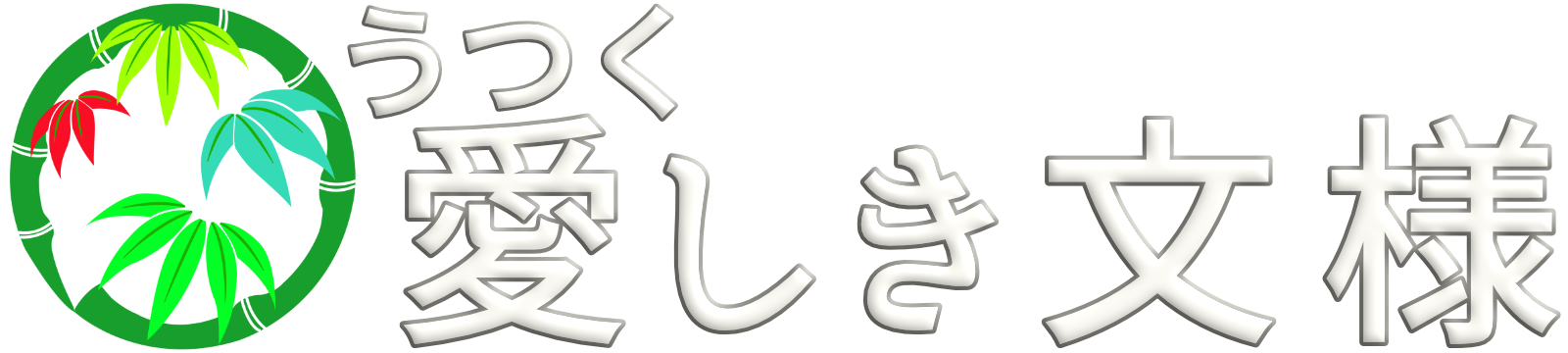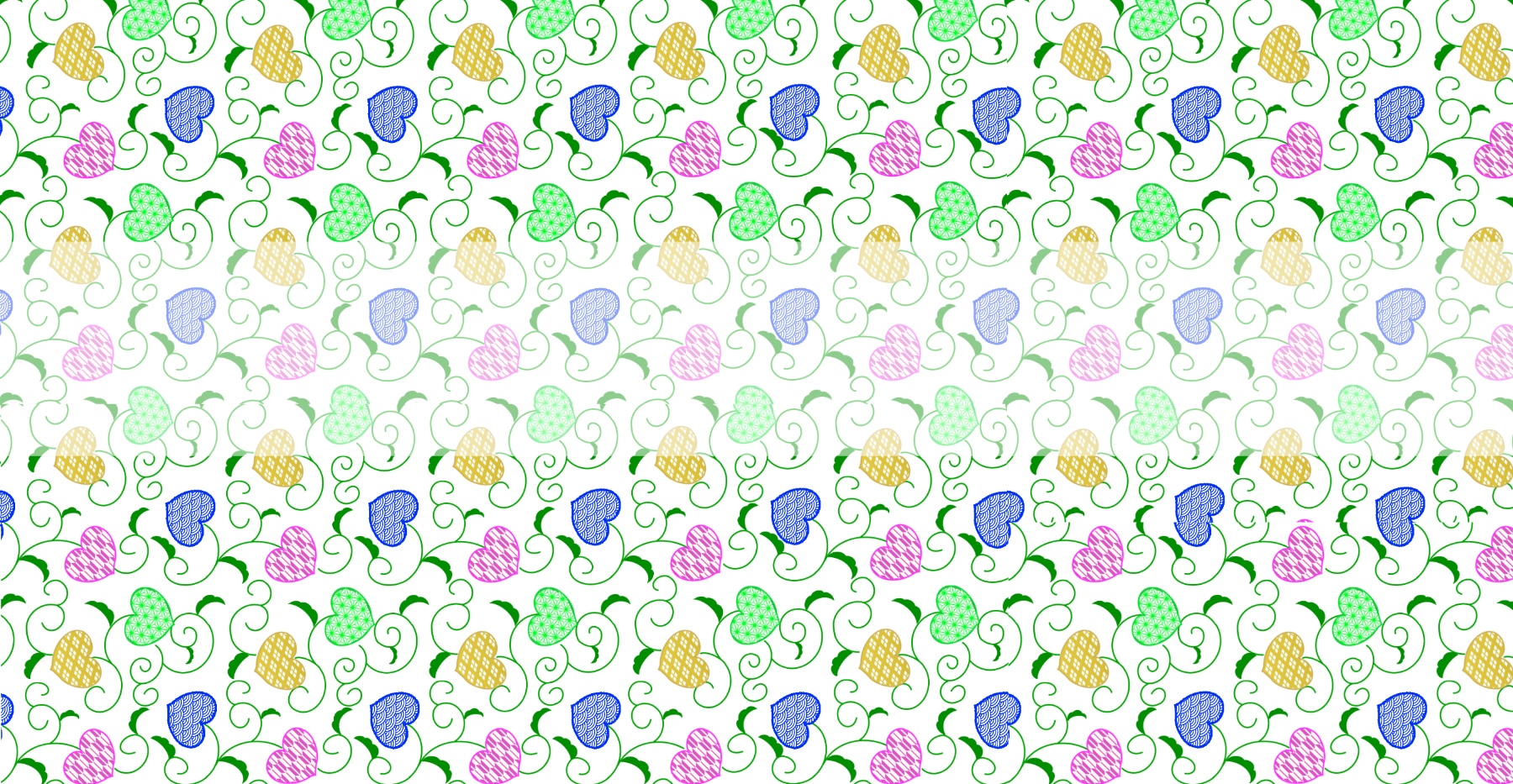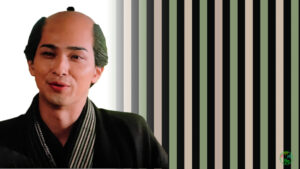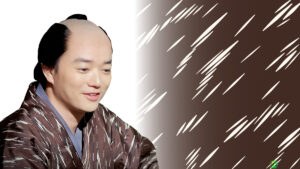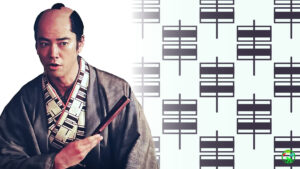目次
吉原 よもやま話
吉原は大きな町だった
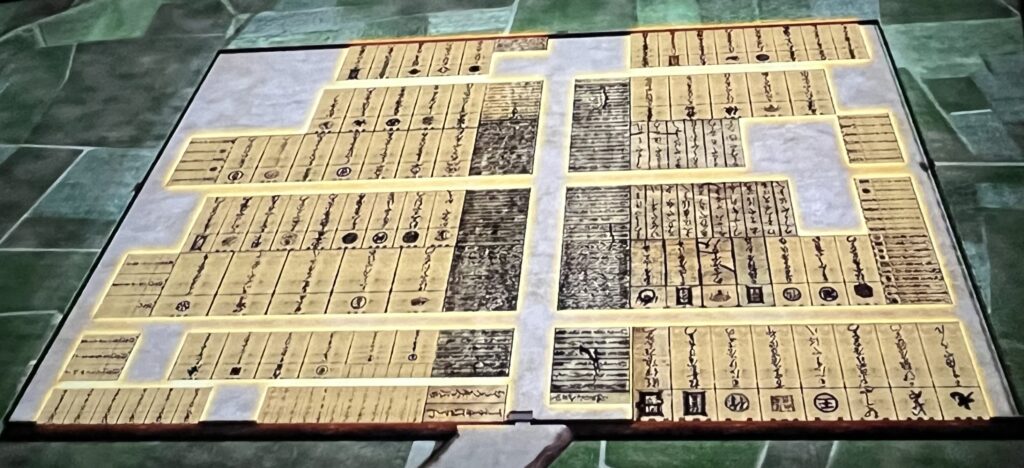
傾城の町、吉原。
遊女が逃げないように堀で囲まれた その町は、なんと2万坪…東京ドーム2個分の広さでした。
吉原にあったのは、遊女がいる妓楼だけではありません。
米屋、酒屋、菓子屋など普通の町にあるような店もたくさんあり、1万人もの人々が住んでいたそうです。 写真 NHK『歴史探偵』より
毎年、植え替えた桜並木

吉原のメイン通り“仲之町”には、季節を先取りした木や花が植えられました。
特に桜が有名で、毎年、春が近くなると数千本もの桜を植えたという記録が残っています。
そして、花が散ってしまうと、桜の木は撤去。
別の花を植え替えたり、秋には紅葉を植え錦の道を彩ったそうです。
悲しや、遊女の一生
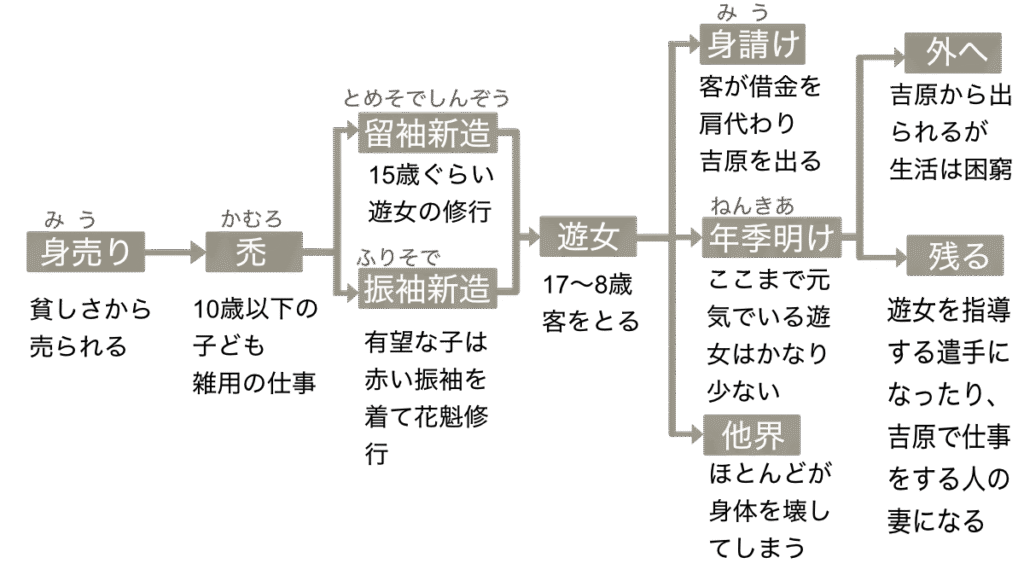
客なのにリンチを受ける?
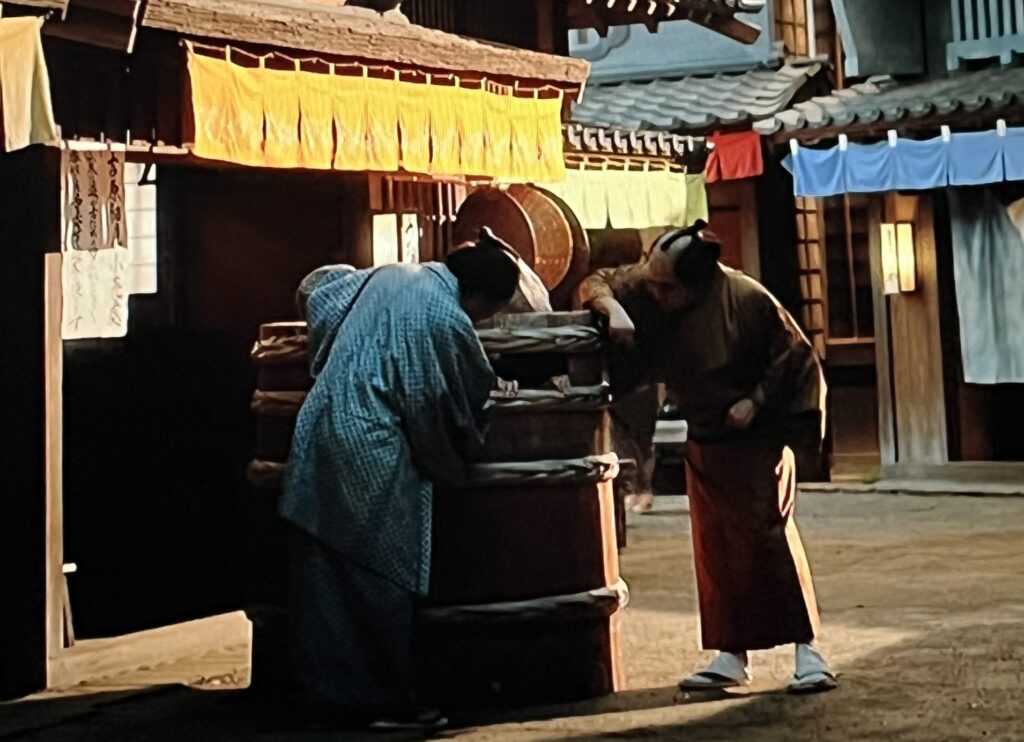
客は、遊女と馴染みになったら、他の妓楼の遊女と遊ぶことは ご法度‼︎
情報は筒抜けの吉原、すぐにバレてしまいます。
帰る時には待ち伏せにあい、馴染みの妓楼に連れて行かれます。
そして、顔に墨で落書きされたり、髷を切られてしまうことも。
お金を払わず逃げようとする客には、きつい折檻が待っていました。大きな桶に閉じ込められ、お金を払うまで何日も帰してもらえませんでした。
吉原は文化サロンだった
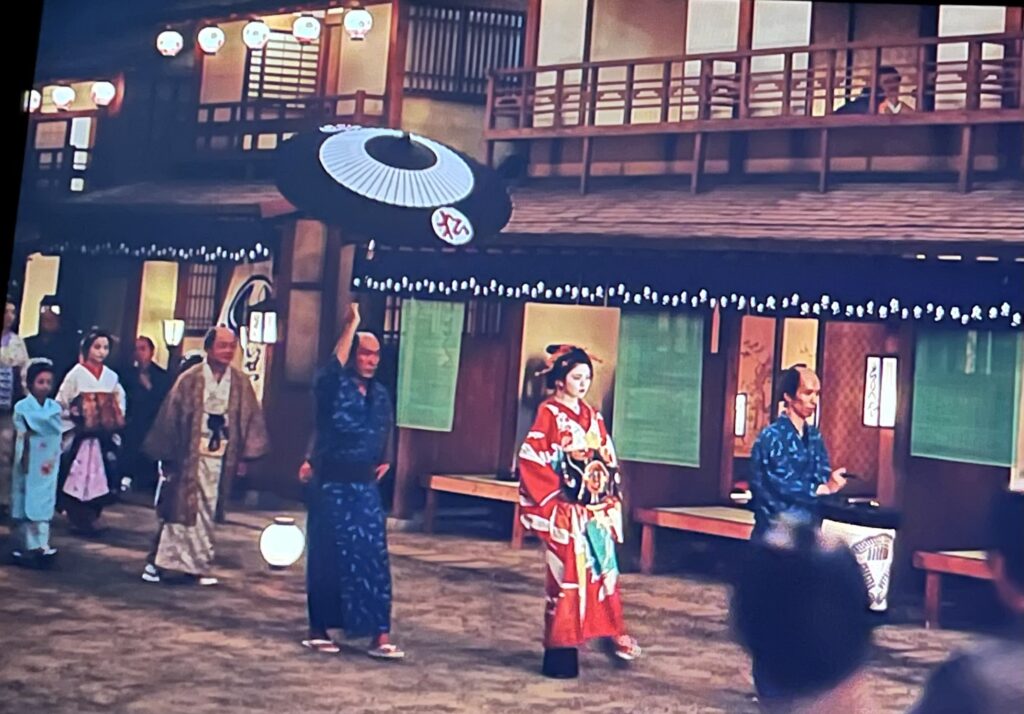
上級遊女“花魁”と遊ぶためには、様々な しきたりやマナーがあり、それらを守ることが客にも要求されました。
まず、茶屋で花魁を待ちます。
花魁は、有名な花魁道中で客を迎えに来て、共に妓楼へ帰ります。
豪華な料理が並ぶ部屋の中、花魁は客に顔を向けず、口も利きません。
こうして 花魁と妓楼が客定めをするのです。
初回は、これで おしまい。
花魁や妓楼に気に入られれば、なんと この手順をもう一度繰り返して、3度目 やっと花魁と床入りとなるのです。

花魁と遊ぶには多額の費用がかかるため、客層は上級武士や裕福な商人たちに限られました。
彼らを楽しませるためには、花魁にも高い教養が求められます。
書道、和歌、楽器、将棋などなど。
吉原は売春だけの歓楽街では、ありませんでした。
粋な文化人が集う社交サロンでもあったのです。
麻の葉文様

大黒屋“りつ”は、ドラマ上での架空の人物ですが、大黒屋自体は吉原に存在した妓楼でした。
“りつ”がドラマで着ていた帯は「麻の葉文様」です。
当時、芸者たちも体を売り始め、遊女と芸者との区別がなくなっていました。
そこで、大黒屋は『見番制度』を作り、芸者たちの派遣や教育、スケジュール管理を一手に担いました。
吉原の遊郭としての質を高めると同時に、収益を上げ、堤防を直したり、下水の整備をしたりと吉原の発展に尽くしたのです。
麻の葉文様
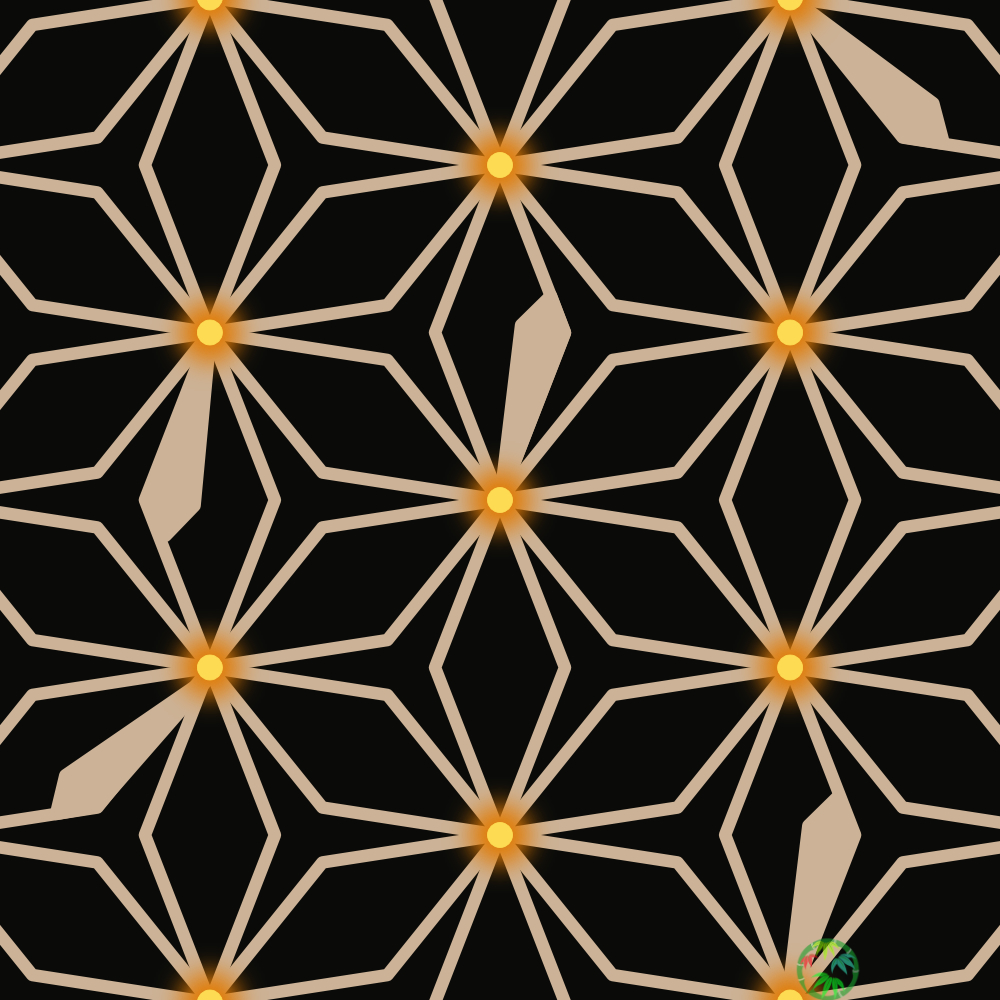

植物の“麻”の葉に似ていることから、名付けられた文様です。
六角形の中に菱形が6つ放射線状に並んだ図柄です。
江戸時代に歌舞伎役者がこの文様を使ったことがきっかけで、庶民に広がりました
麻は成長が早く、真っ直ぐに丈夫に育つため、子どもの健やかな成長への願いが込められています。
また、六角形の形には魔除けの意味もありました。
あわせて読みたい


籠目文様 〜〜 大河「べらぼう」 花の井の衣装より
松葉屋「5代目瀬川」は吉原の花魁。桜の花に例えられるほど美貌と才覚の持ち主でした。ドラマで普段着の着物は「籠目文様」。花魁として名を轟かせても、所詮遊女の悲しさを「籠の中の鳥」として表現しているのでしょうか?